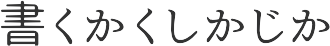すごい映画を見てしまった。監督・川島雄三、脚本・新藤兼人による『しとやかな獣』。
若尾文子を見たくて見たこの映画であったが、若尾文子の美貌以上に恐れおののく人間の醜悪と、貧しさと豊かさが生み出す狂気を、皮肉たっぷりに冷徹なユーモアを込めて描かれた大傑作のブラックコメディ映画だ。普通の映画じゃ満足しない、ちょっとひねくれた映画を好む方には、ぜひ見ていただきたい至極の一作。(ネタバレあり)
◆目次
檻の中の獣
「ヨーッ!」と、能のお囃子から幕が開くように物語が始まる。鼓の雅な音色とは裏腹に、映像の始まりは高度成長期当時モダンで憧れの的だった「団地住まい」のある一室。なんとこの映画の舞台は団地の一室、のみだ。
住人は、元海軍中佐でありながら無職の父前田時造(伊藤雄之助)と、その妻よしの(山岡久乃)。娘(浜田ゆう子)は売れっ子作家(山茶花究)の二号さんで、娘を使って前田家に金を入れさせ夫婦は悠々自適の生活を送る。息子の実(川畑愛光)は芸能プロダクションで働くも、会社の金を横領し、これまたその一部を前田家に入れさせるという、真面目で勤勉な日本人はどこにいってしまったのかと、嘆きたくなるような欲に埋もれた守銭奴一家。
そしてこの一家の上を行くのが、芸能プロダクションで会計の仕事をする三谷幸枝(若尾文子)で、実が熱を上げる。三谷は金を引き出すために、女であることを利用しながら実のほかにも、芸能プロの社長(高松英郎)や税務署の神谷(船越英二)とも次々関係を持っている。それでいて念願の旅館を開業し、大業を成し遂げたら全ての男との清算をはかるという、美女の皮を被った獣として登場する。
人物の紹介はこれくらいにして、この映画の面白さは、前田家で起こる悪党たちの所作を、団地の一室という閉ざされた「檻」を、高みの見物とばかりに冷静に眺めるところにある。前田家という世にも奇妙なエゴ丸出しの獣たちが暮らす檻の中を、悪趣味にも内から外から上から下から、その生態を執拗に観察する。観客はまるで、珍しいホモサピエンスに目を凝らす生物学研究者だ。
実験的で斬新なカメラワークが表す、いびつな世界観
閉ざされた団地の一室のみを映し出すという新鮮で奇抜な試みは、あらゆる角度・あらゆる陰影・あらゆる奥行きによって巧みに構成された驚きの”絵”を実現させた。
ベランダから見た団地の内部。壁を区切りに左右の2部屋の空間を映す絵は、中央で分かれた1枚の絵画のよう。また団地の鉄製扉ののぞき窓の向こう側にいる人物と、扉の手前にいる人物が同時に撮ることで、奥行きを表しながらも、不思議な平面絵のようでもある。3次元空間を、映像で2次元的に表現するという見せ方の工夫が際立っている。
戦後の泥を飲むような貧乏生活を回想するシーンでは、前田家・家族4人それぞれが静止し、母・娘・息子・父と順にシリアスな表情をアップで映す。まるで漫画のコマ割りのような映像を展開した。漫画調の表現はここだけに終わらず、会計の三谷と芸能プロダクション社長とが無言で会話するシーンにおいても同様。二人だけにスポットライトが当たり、二人は静止したまま心の声だけが響く。舞台の芝居のようでもあるが、神妙な表情を静止させることで漫画の「効果線」にようにリアリティを強調し、心情は心の声だけで表現する手法は、漫画の「吹き出し」に似た表現だ。
何度か登場する象徴的シーンとしては、階段。階段は人生の上り下りを表していて、得る物を得れば階段を上り、地位や名誉を失えば階段を下りる。その階段は真っ直ぐで真っ白い、白の単色と、階段の線で構成された抽象絵画のような不思議な世界。
さまざまな趣向を凝らした演出の中、もっとも印象に残るのは、団地へ刺す真っ赤な夕焼けの光の中、下着姿で雄叫びあげながら、狂ったように強烈なゴーゴーダンスを踊る姉弟。そんなたぎる若さの放出をよそに、夫婦はもくもくと蕎麦を食べ、たんたんと後片付けをする。まさにシュールレアリズム。バックには、激しく撃ちつける鼓の音。次第に強さを増す鼓と共に、姉弟の踊りも異常さを増す…。(このシーンを見て確信した。この映画は名作だ!)
このように、通常とは違うおかしな視点・おかしな構図と、おかしな設定をふんだんに入れることで、この物語が持ついびつな世界観を顕著に表現している。
悪いやつほど、よく生きる
口では高尚な言葉を並び立て、腹では下衆を極める父の伊藤雄之助には、苛立ちを禁じ得ない。キャビアやブルーチーズを食べ、昼間っからビールを煽り、くすねた金で投資。娘を作家の愛人にし、それを担保にひっきりなしに金を無心する。息子が女に入れあげ大金をつぎ込んだと知ると、そんな金があるなら父に回せと嫉妬を剥きだす。
母の山岡久乃は優雅にふるまいつつも、そんな父を援護し同様に金を無心する。お上品でお口も計算もお上手な悪女。そこへいくと娘の浜田ゆう子は可愛らしい小悪魔だ。関係が終わりそうになっている作家へ、父の命令通り金を借りる話を持ち出し、当然のように振られてしまうのだから。棒読み演技が気になる息子の実は、この親にしてこの子ありを見事に体現した強欲屋さん。
そして麗しの若尾文子は、この映画では美しい顔をして明け透けに物を言う大悪女。「お金をいただく代わりに、私を差し出したわ」なんて台詞を、さらりと言ってのける。その美貌と度胸なら、貢がれた金で旅館が建ってしまうことも納得できる。
いろんな悪党がひしめき合うなか、観客にも悪党を味あわせる演出も。その演出の一部が、あらゆる角度から功名な絵を描くカメラワークである。芸能プロダクションの社長(高松次郎)が倒産の危機に慌てて前田家にやってきた時、そして税務署の神谷(船越英二)が最期の別れのため、若尾文子に会いに前田家にやってきた時もに発揮された。
人生で一番の窮地と言うべき人間の表情を真下から捉えることで、そのうろたえ困り切った表情を、鼻の穴までまじまじ見てやろうという悪趣味な表現がそれだ。まるでいたいけな子供を、死の淵まで追いかけまわすいじめっ子のようである。そうやって見る者の善良性も麻痺させるように、地味だが確実に効く「いやさしさ」がこれでもかとぶち込まれている。
いじめられっ子の善人が不条理に泣き、いじめっ子の悪党がのうのうと世にのさばり守られてきた秩序を破壊しながら、新たな秩序を正当化する。まったくどうしようもない「人間の不公平感」を映画として描いているが、皮肉なことに映画公開から約60年後の現実社会では、誰しも日常的に感じていることだろう。川島雄三監督は、軽薄になりつつある日本人への警告をブラックジョークで見せてくれている。
団地の数だけ、「獣」が生まれる
最後は大雨が降りしきる中、作家に捨てられた娘を含む前田家の家族4人が、それぞれ思い思いにくつろぐ中、三谷の公算とは逆に、結局税務署の神谷は自殺する。
神谷が自殺したことで、うまく上ったはずの階段を焦りの表情で駆け降りる若尾文子とは反対に、山岡久乃が見せた表情は、この映画での”しとやかな獣”とは、山岡久乃であったと指示しているのだと、私は解釈した。
神谷の身投げを知った山岡久乃の、諦めとも言えず、焦りとも思えない神妙で”しとやか”表情は、静かだが冷たい恐ろしさを孕んでいた。(さすがの女優は、表情だけでおぞましさを表現する)
息子の実が捕まることを認知した悟りの表情だろうか、それとも例え息子が捕まろうとも自分だけは逃れようと企んでいるのだろうか、またはいつも通り知らぬ存ぜぬでやり抜こうと覚悟を決めた表情なのか。前田家の”いびつさ”は饒舌な父によって生み出されていたと思いきや、表面では丁寧なお言葉遣いで上品さを気取り、内面は冷酷で秩序を狂わす母によって生み出されていたに違いない。
さてこの映画は、ある一家の異常な醜態を描いただけの映画であったのだろうか。
山岡久乃の神妙な表情の後に映るのは、鼓と笛がおどろおどろしく心を掻き立てる能の囃子を背に、遠くから捉えた団地数棟。そこには前田家同様に、高度成長期に物を食べ排泄しもっと豊かな生活を夢見て暮らす数百の家庭が存在する。
苦しく貧しい生活から一変、戦後驚異的速度で変わる高度成長の価値観の元、前田家は人間の底知れぬ欲を正義とする”模範的”ないちサンプルに過ぎない。貪欲に資本主義経済を突き詰めれば詰めるほど、和をもって尊しとしてきた日本人が、完全個人主義の悪魔へとすり替わり、反比例するように道徳理念が退化する。
団地の数だけ、家庭の数だけ日本のあちこちで、道徳を失い拝金主義に取りつかれた「獣」が溢れることを予見したかのような余韻を残す、そんな不気味な終わり方であった。