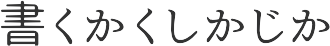見よ!晴れた空よりも美しく眩しい若尾文子の姿を。以前よりずっと気になるポスターであったこの「青空娘」を、ようやく鑑賞することができた。監督は増村保造で、若尾文子とは約20本もコンビを組むことになる。その初タッグとなる映画が、この「青空娘」である。
◆目次
あらすじ
祖母に育てられた有子(若尾文子)は、実の母は別にいることを告げられる。高校卒業と同時に東京にいる父母のもとへ引き取られることになったが、継母や異母兄弟からは女中の扱いを受け、それでも必死に東京にいる実母を探す。有子の健気で可憐な姿は、高校の恩師・二見(菅原謙二)や異母姉の恋人候補の広岡(川崎敬三)の心を射止めてしまい、この二人の男性の助けで、実母との再会を果たすことになる。
物語の鍵は「晴れ」、曇り空から青空へ
映画の前半の主人公・有子は、可哀そうな灰かぶり姫。実父を訪ねた東京の家は大邸宅で、継母のいじめに遭う。女中として働かされ、与えられた部屋は階段下の汚い倉庫。異母姉の婿探しパーティーでは、気立てのよさから異母姉ではなく女中の有子が見初められてしまい、異母姉は嫉妬に狂う。いつでも味方をしてくれるのは、先輩女中の八重(ミヤコ蝶々)と末っ子の異母弟と時々魚屋。前半までは、王子が現れる前のシンデレラそのものだ。
後半はガラリと変わって、遠慮がちだった有子がどんどん大胆な「女」に変わっていく。住む家がなくなった有子は、男の一人暮らし恩師・二見のアパートへトランクを持って一人乗り込む。そこが駄目だとなると、今度はプロポーズはされたものの宙ぶらりんに保留していた広岡に、お金を借りに押し掛ける。最後は実娘を女中にさせておいても妻(継母)に文句も言えない、そして愛がないと言いながら別れることもできない中途半端な実父を一喝し、霧がかった空を、スカッと青空に変えてみせた。
青空に告げる、別れの言葉
心の晴れ模様を表すこの映画の二面構成を、いっそ色濃く表現していたのが、有子を巡る恋のライバルである二人の男性の存在だ。一人は高校の恩師・二見と、もう一人は異母姉の婿候補だった金持ちの広岡。
東京行きに心が曇る有子に、二見は「青空はどこにいたって見える、目を瞑ったて見えるんだ」と勇気づけ、田舎の見慣れた青空に別れを告げる。二見が「あばよ」と叫び、有子は「さようなら」と叫んだ。それがこの映画の始まりのシーンだ。
結局有子はその後現れた広岡を選ぶことになるのだが、最後のシーンでは広岡が「僕が君の青空になる」と、青春映画らしい気障なセリフを飛ばし、再び有子は青空に別れを告げる。広岡が「さようなら」と叫び、有子が「さようなら」と叫ぶ。
映画冒頭のシーンで、お天気雨のように違和感のあった二見と有子の別れの言葉が、広岡と有子で最後はぴったり一致し、晴れやかな気分になったのだった。
台風の如く進むストーリー
シンデレラが幸せを掴む一見ありがちなストーリー。それでも飽きることなく見てられる理由に、ストーリーの疾走感がある。黒く染まったオセロを、順通り白に裏返すように、テンポよくストーリーはどんどん進む。次から次へと話が展開するため、実の娘が女中扱いされる悲壮感や、母に遭えない苦しみはさほど感じず、劇中ずっと爽やか。
ストーリーを軽妙に運ぶんでくれたのは、脇を固める役者のフットワークの良さにある。まず先輩女中・八重役のミヤコ蝶々。突然有子の前に現れ、「ヘイ!タクシー」と勇ましくタクシーを止める。ブルジョアやブレックファーストなどの横文字を使いこなし、上流家族を皮肉る。そこへ来る馴染みの魚屋屋もまた八重と同じように関西弁を操り、首にクロスを掛け哲学を懇々と説く。2人の掛け合いはまるで漫才。丁寧にオチまで用意されている。そしてもう1人、有子がお世話になるキャバレーの女将。はっきりした性格で、女将にかかれば、「了解!」の一言で二度は言わせない。
なんだか可笑しくて気持ちが軽くなる。芸達者な脇役の喜劇によって、台風の日の雲のように、話はスピードに乗って流れていく。
若尾文子の軽やかさ
一方で、若尾文子の良いところも「軽やか」であることだ。
あの麗しの美貌と、低音で艶のある特徴的な声とは裏腹に、若尾文子が案じる「女」は、どこか足歩取りが軽く、言いにくいこともあっけらかん言ってのける可愛い図々しさがある。
「青空娘」でも、その「軽やか」さは発揮されている。現実を見ず幻想の有子にすがる実父。そんな実父に、有子は静かに雷を落とす。
「お父様は生ぬるいのよ」
健気で献身的であった有子が、実父に放った鮮烈な言葉だ。しかしその言葉には、ドロドロした恨み節やかき乱すような情念はまるでない。綺麗さっぱり「さようなら」と軽やかに去る。実父を捨てるという重苦しいシーンでも、若尾文子だからこそ、裏表のない清潔な爽快感を醸し出せるのだ。二見と広岡、純粋そうに見えて二人の男を利用することろもまた、堂々と厚かましくて潔い。
1960年代に入りさまざまな悪女を演じる時にも、その爽快感は小気味よく表現されている。例えば「刺青(1966年)」。「青空娘」の時の美貌に妖艶さが増し、なまめかしい若尾文子演じるお艶は、男を狂わせた挙句恋仲の新助に始末させるという、男の血を吸い取るような悪女を演じた。これも若尾文子ならではで、怯える新助をよそに、さっぱり爽やかに新助に殺人を繰り返させる。演じる若尾文子の透き通る白い肌と軽快な口調は、陰鬱さを微塵も感じさせない、だからこそ冷血非道な悪女を演じ抜ける。
1957年(昭和32年)に公開された「青空娘」は、若尾文子が24歳の時になる。デビューが19歳であるから、若尾文子にとって比較的初期の作品にあたる「青空娘」は、若尾文子のあどけなさが残るフレッシュな中にも、後に同じく増村保造作品において妾や女郎で男を翻弄する悪女を演じる女優・若尾文子の片鱗を、少し垣間見ることができる明るく爽やかな良い映画であった。