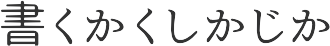人を感化する芸術家の言葉は、時を超えて普遍的に輝き続ける。その言葉をその息づかいを、すぐ隣で聞くことができたなら・・・2010年代を生きる主人公の時空冒険を、1920年代ピカソやヘミングウェイなどの芸術家が集う生き生きとした花の都パリを舞台に、エスプリを効かせて鮮やかに描かれたアメリカ映画『ミッドナイト・イン・パリ』。
ウディ・アレンが監督・脚本のこの映画は、第84回アカデミー賞で脚本賞を受賞した。『ミッドナイト・イン・パリ』に登場するエポックでポエティックな名言の数々を、映画と共に紹介する。
◆目次
あらすじ
ハリウッドの脚本家・ギル・ペンダー(オーウェン・ウィルソン)は、婚約者のイネズ(レイチェル・マクアダムス)と共にパリに滞在、同時に処女小説に取り組んでいた。懐古主義のギルは雨が美しいパリの街に浸るが、イネズはパリの嫌な雨よりも、博識でフランス語を流暢に話すもの知り顔のポールに夢中。
ある夜の午前零時の鐘が鳴る頃、アンティークのプジョーが1台ギルの前に現れた。パーティーに向かうその車に、誘われるままに乗り込むが、着いた場所にはF・スコット・フィッツジェラルド(小説家)と妻ゼルダ(小説家)、ピアノを弾くコール・ポーター(作曲家・作詞家)にジャン・コクトー(芸術家)・・・いつの間にやらギルの愛して止まない1920年代のパリへタイムスリップしていたのだった。
1920年代のパリで、モディリアーニ(画家)やピカソ(画家)とも浮名を流す美女アドリアナ(マリオン・コティヤール)にギルは一目惚れし、ますます1920年代へ傾倒していく。
ハリウッドの脚本家としてマリブで暮らしたい婚約者と、小説家として自身の表現法を磨くためパリでの生活を望むギル。婚約者イネズと価値観が合わないと気づきつつも自分を誤魔化し生活するギルは、過去の女性を好きになりどのような道を選ぶのか。
見どころ
この映画の見どころは、何と言っても1920年代パリに芸術家が一同に集まっていることだ。
日本に関係する芸術家で言うならば、乳白色の裸婦像が有名な画家・藤田嗣治が、パリで活躍し多くの芸術家と交流していたのがちょうど1920年代になる。この時代に精通していれば、もちろんこの映画の細部まで楽しめるだろう。しかしそうでなくても十分楽しめる。
実際私は恥ずかしながら文学方面には疎く、フィッツジェラルドやガートルード・スタインといった文豪を知らなかった。映画を見終わった後に調べてみると、劇中に登場する芸術家とそっくりな外見をしていることに驚かされる。時代背景やどのような作品を残しているのかなど、実在する登場人物を後で調べてみるもの、楽しみのひとつである。1920年代と1890年代の画家が出てくるため、シュールレアリズムがどのようなものかなど、美術史を少しでも知っていれば十分に分かる内容である。
また芸術の息吹が芽生え花開き、街にカフェにと文化がスパークしているパリの雰囲気を味わえるのも、まるで過去に焦がれる主人公・ギルになったような気分で、胸が躍る。多くの日本人がフランス・パリに抱くエレガントで豪華なイメージよりも、人々が生き生きと文化を楽しみ、生命を爆発させる活気に満ちた夜のパリを、主人公と同じ気持ちになって味わうことができるのだ。
時空を超えて心に残る言葉・名言
この映画はアカデミー賞をはじめ多くの脚本賞を受賞している。また主人公ギルの本業も脚本家であり小説家である。そのためか、この映画にはコントロール不能な人生に悩む解毒剤となるような、胸にストンと落ちる名言が散りばめられている。
真実があれば・・・
1920年代にタイムスリップした最初の夜に、主人公ギルはアーネスト・ヘミングウェイ(コリー・ストール)に、自分はどのような小説を書くべきかを尋ね、帰ってきた言葉がこれである。
No subject is terrible if the story is true, if the prose is clean and honest, and if it affirms courage and grace under pressure.
そこに真実があるのなら、そして絶望の中の美学を肯定するのなら、それ以上に優れるものはないということだ。逆に言えば、それが上辺だけの真実であるなら、また絶望を絶望のまま描くなら、書くべきではないということ。
ギルの婚約者イネズが敬愛する男・ポールが、ガートルード・スタイン(キャシー・ベイツ)や美術館ガイドの女性(カルラ・ブルーニ)には、ただの”うんちく垂れ”にしか見えないように、真実がなければ陳腐に見えるということだろう。
同様のことが、主人公ギルが小説の講評を求めたガートルード・スタインから出た名言にも見て取れる。
The artist’s job is not to succumb to despair,but to find an antidote for the emptiness of existence.
監督・脚本を務めたウディ・アレン自身が、この真理に基づいて制作に臨んでいるのではないかと感じる。
主人公・ギルは懐古主義を「苦悩する現代へ拒絶」などと揶揄されながら、現代での生き難さ感じていた。しかし、この映画を見る多くの悩める人を解決に導くように、その空虚さから最後には救われることになる。
愛と死
ヘミングウェイが戦争について話し、その上でギルに婚約者と愛し合う時に死の恐怖を忘れることができるかと尋ねた。
I believe the love that is true and real,creates a respite from death.
ギルは婚約者イネズにそのような感情を持たないこと、つまりイネズと居ても死の恐怖はなくならないと告白している。それは、ギルのイネズに対する感情は”真実”ではないことを暗に意味している。
ではなぜ”真実の愛”とやらは、死という必ず訪れず絶望を恐れずに済むのか。
それは、死を追い払うに値する情熱が充満しているからだとヘミングウェイは言う。
「愛」を語る表現にしては、猛々しい雰囲気もあるが、誰もが納得できる真実であろう。
ボクシングとサイ
劇中、ヘミングウェイが唐突に「ボクシング」という言葉を持ち出すシーンがある。また、サルバトール・ダリ(エイドリアン・ブロディ)の登場シーンでは、「サイについてどう思うか」という奇妙な質問から始まった。
実際のヘミングウェイは、ボクシングや闘牛を好むマッチョな男であったし、ダリが好んで作品のモチーフにした物のひとつが「サイ」である。
要所要所に人物の象徴的なキーワードを入れながら、高尚なものまねショーを見せられているように、くすりと笑える遊びの要素が入っていて、実に楽しい。
さらには、「実は、未来から来ている」と耳を疑うような告白するギルをよそに、3人のシュールレアリストは驚きもせず4段オチ(シュールレアリズム・ギャグ)を決めてくれる。
ルイス・ブニュエル:映像が見える
ギル:どうにもならない問題が見える
ダリ:サイが見える
Man Ray: A man in love with a woman from a different era. I see a photograph!
Luis Bunuel: Isee a film!
Gil: I see insurmountable problem!
Salvador Dali: I see a rhinoceros!
台詞から分かる通り、マン・レイは写真で活躍し、ルイス・ブニュエルは映画監督として才能を開花させ、ダリは芸術家として世を驚かせた。
いつだって過去は輝かしい
2010年代のギルは1920年代に憧れ、1920年代のアドリアナは1890年代のベル・エポックこそがゴールデンエイジだと言う。そして、ドガやゴーギャンはルネサンス期こそがゴールデンエイジで、もっと昔に生まれるべきたったと。
Maybe the present is a little unsatisfying because life is a little unsatisfying.
例え誰の人生に生まれ変わっても、現在とは不満なものである。仕事が楽しくない、人間関係がうまくいかないなど、上げればきりがない。だからこそ、ギルは憧れの時代に思いを馳せた。”今とは違うもの”を切望する気持ちは、懐古主義でなくても同じではないだろうか。
人は「今」から逃げるために、新しいものを求める。そして苦労して得た「新しい」ものは、慣れてしまえばやがてまた「古臭い」ものになり、「新しい」ものを求め彷徨い続ける。映画の中で、憧れていた1890年代のパリへ留まることを決めたアドリアナに、いずれまた別の時代に憧れるようになると、ギルが忠告したように。
一方のギルは気づいてしまった、終わりのない幻想のループに。価値のあるものを書こうと思えば、幻想は捨てるべきであることに。ギルは、現代のそして彼自身の”ゴールデンエイジ”を創造する道を選ぶ。
最後に
 『ミッドナイト・イン・パリ』は、テンポがよくユーモアいっぱいで、大変面白い映画である。しかし流れるショーの要素が、この映画の面白さを強めているのではない。そこに、パリの活気ある空気感やゴールデンエイジに感じる美学を、心の底から好きだという真実と情熱が、映像・台詞・音楽など映画の中に詰め込まれているからだ。
『ミッドナイト・イン・パリ』は、テンポがよくユーモアいっぱいで、大変面白い映画である。しかし流れるショーの要素が、この映画の面白さを強めているのではない。そこに、パリの活気ある空気感やゴールデンエイジに感じる美学を、心の底から好きだという真実と情熱が、映像・台詞・音楽など映画の中に詰め込まれているからだ。
今とは違う時代に憧れどっぷり浸かり、すっかり出れなくなったかと思われギルであったが、ガートルード・スタインの名言の通り、1920年代と1890年代の芸術家によって”存在の空虚さから抜け出す解毒剤”を得て、現代にそして未来に希望を見ることができた。
そしてラストは、午前零時の鐘と共に、雨のパリをこよなく愛する女性がギルの前に現れる。恐らく彼は、彼の美学をもとに2010年代で彼の”ゴールデンエイジ”を創っていくのだろうと、想像させるポジティブな気分で幕を閉じた。
「今」を生きることに疲れた時、つかの間の幻想を優雅に小気味よく味わえる映画として『ミッドナイト・イン・パリ』をおすすめする。
しかしくれぐれも、アドリアナのように過去の住人になることなく、”現代のゴールデンエイジ”に戻って来ることだけは、お願いしたい。